『現場内小運搬』とは? -不可能を可能にする機材の搬入の必殺技-
地質調査における『現場内小運搬』とは?
地質調査(ボーリング)を行う場合、調査を実施する現地まで調査に必要な機材を車両等を使って運ぶ必要があります。
通常は、ボーリングマシンやポンプ、櫓を組むための単管パイプやクランプと工具類、ロッドやケーシング、セメントやベントナイト等の材料、採取した試料を収める標本箱などが必要な機材となります。
井戸の掘削工事やその他の土木工事などに比べると、ボーリング調査に使う機材は小型で、比較的コンパクトに運搬することが可能です。
そのため、一般的にはユニック車といって、クレーン装置の付いた2~4tのトラックを使用して、まず倉庫などから現地までの機材運搬を行います。
この機材の運搬を、『資機材運搬』と呼ぶことが多いです。

地質調査に携わる業界にいると、普段道路でもボーリングマシンを積んだトラックを見ると気になってすぐ目に留まるようになります。機材の積み込み方が美しいと、見とれてしまうこともあります。
こうして現地まで機材を運び、調査地点付近までトラックが進入できる場合には、車両に搭載されたクレーン装置を使って各種の機材を調査地点に降ろして行きます。
このように直接調査地点に機材を降ろせる場合は比較的運搬としては容易になります。作業へのとりかかりもスムーズに行えます。

このように機材を調査地に降ろすことを『搬入』、調査後に撤去することを『搬出』と呼びます。
上の写真のような現場だと、まず小さな機材等を人の手で降ろし、ボーリングマシンを設置するための足場を組んだ後に、クレーン装置を使って直接搬入することができます。
ユニック車にも様々な規格があり、搬入可能な調査地点までの距離や高低差等には限界がありますので、事前の現地確認と車両や足場の設置計画が重要になります。
そして、上記のように直接トラックから調査地点へ機材の搬入が難しい場合に行うのが『現場内小運搬』と呼ばれるものです。
国土交通省から出されている『設計業務等標準積算基準書』によると、
現場内小運搬は、ボーリングマシン並びに各種原位置試験用機材をトラック又はライトバン等より降ろした地点から、順次調査地点へと移動して、調査終了後にトラック又はライトバンに積み込む地点までの運搬費である。
国土交通省
と定義されています。
現場内小運搬が必要になる場合としては、調査地点まで車両が進入できる道路が整備されていない(道幅が狭い、災害等による影響など)ということです。
地質調査を行う場所はさまざまですので、その現場ごとに臨機応変に運搬方法を検討する必要があります。
一般的よく用いられる『現場内小運搬』の方法としては、
・人肩運搬
・特装車(クローラ)運搬
・モノレール運搬
・索道(ケーブルクレーン)運搬
が挙げられています。そこで、一般的によく使われる現場内小運搬の方法について少しだけ解説していきます。
(索道運搬については、それ自体がかなり大規模な装置になることが多く、地質調査は工期が比較的短いこともあり、あまり採用されませんので、ここでは説明を省略します。)
様々な現場内小運搬の方法
・人肩運搬
まずは、人肩運搬です。これはもう読んで字のごとく、人が肩に担いで機材を運搬する方法です。
一番原始的な方法で作業をする人の体力も使いますが、最後はこの運搬に頼らざるを得ない場合もあるのが現実です。慣れるまで(慣れても?)は、肩がとても痛くなりますし、コツをつかむまでは結構大変です。

比較的短距離の運搬で、後でご紹介する特装車も進入できないような狭い(幅50cm以下)通路しかない場合などに用います。また、緩い傾斜地であれば、対応可能ですが、足場が悪いと転倒などの危険が伴う上、運搬効率も悪く、体に掛かる負担が大きいため、できるだけ他の運搬方法を選択したいところです。
ベテランの機長さんの中には『担いだ方が早いよ!』と言われる方もいます。確かに、作業の効率化と期間短縮も重要です。
しかし、事故の防止や作業する方の安全や健康はそれよりも優先すべきことです。そのあたりをしっかり検討したうえで、最善と考えられる運搬方法を選択することが必要です。
・特装車(クローラ)運搬
次に、特装車運搬です。不整地運搬車とも言われるもので、未舗装などの整備されていない道や車両だとタイヤが埋まって動けなくなるような場所などを運搬するために使用します。ボーリング調査の際に使われるのは、比較的小型のものになります。


特装車運搬は、調査地点まで車が近づける道がない場所などで活躍します。人肩運搬に比べ、一度に運べる機材の量も多くなることに加え、体に掛かる負担がかなり低減できます。傾斜地でも20°までくらいの場所であれば登れます。
その現場での使用する機材の量や調査地点までの通行できる道幅などにより使用する特装車の大きさを変えます。
ただ、この場合に気を付けなければいけないのは、調査地点に行くまでに調査地点とは別の人の私有地等を通る場合です。
特装車を使う場合は、調査地点までの直線的な移動ではなく、迂回するようなルートで搬入することも少なくありません。
そのように他人の土地の中を通る場合は、必ず事前に役所や土地の所有者への連絡を行い、許可を得なければなりません。さらに草木の踏み荒らしなどは最小限に留めることと、出来る限りの原型復旧を行うことを忘れてはいけません。
そもそもこの特装車自体もトラックに載せて現地までは運ばなければならないこと、トラックから一度特装車に積み替えを行うための開けた場所が必要になるなどのデメリットもありますが、人肩運搬に比べると安全性も高く有効な運搬方法といえるでしょう。
・モノレール運搬
最後はモノレール運搬です。一度は言葉ぐらいは聞いたことがある人も多いかと思います。専用のレールを設置し、そのレールの上を機材を積んだモノレールで走行する運搬方法です。



モノレール運搬の強みは、既存の運搬路や道路がなくても設置が可能なことと、ある程度急な斜面でも対応ができることです。また一度レールを設置してしまえば、あとはその上を移動するだけなので、運搬に関しての労力はかなり低減されます。人肩運搬も特装車での運搬も難しい場面で大いに活躍します。
しかし、運搬自体は楽に行えるものの、レールの設置は大変です。専門的知識と経験が必要であるため、専門の業者に依頼することも多いです。
道なき道を進むため、調査地点までのルート選定が非常に重要になり、設置場所の草木の伐採も必要です。
ルートを選定したらその設置距離を測り、必要なレールの資材を準備し、現場まで持ち込まなくてはなりません。そのためモノレールはその設置と撤去に大きな労力と時間がかかることが多いのです。
ただ、災害で被災した場所での調査や、山奥の砂防堰堤(外部リンク) などの調査においては、非常に重宝する運搬方法です。
その他にもある、現場に応じた運搬方法
突然ですが、ここで問題です!
下の写真のような調査地点にマシンを搬入する場合、どんな方法を使ったでしょうか?

3
2
1
0 正解は、『ラフテレーンクレーンを使った』です!
『そんな運搬方法は紹介してないじゃないか!』と言われそうですが、すいません。
この現場は災害復旧工事の現場だったのですが、人肩やクローラではもちろん不可能でした。
モノレールを設置するにしても、安全なルートでは大きく迂回する必要がありました。加えて、ボーリング自体は比較的短期間で完了する見込みでしたので、

このように大型のクレーンを手配して高い場所に一気に機材を搬入しました。この場合もその場所までの道路が必要だったり、クレーンが停車できる十分な広さの平地が必要です。調査地点までの水平距離や高さには制限がありますが、有効な運搬方法の一つです。
ちなみに、上にある道路から、低い位置の調査地点に吊り降ろす場合もあります。


また、海や川での調査を行う際に水上に足場を組む場合があります。そんな時には、船を使ったり、岸から近い場合には仮設の桟橋を造り、その上を人肩運搬などで運ぶこともあります。


2枚目の写真は、河川の中州で調査を行った際のものです。水深は浅いものの、川を渡らなければ調査地点に行けなかったので、中州へロープを渡し、機材を濡らさないために小型のボートに機材を積んで運搬を行いました。これはかなりレアケースだと思います。
これらの運搬方法の他にも、軽トラックを使った運搬や山上などではヘリコプターを使った運搬など、機材の運搬方法には多くの種類があります。
地質調査の技術者は調査現場を見て、どの運搬方法で、どのようなルートで機材を運ぶのが、1番安全で、効率的かつ低コストかを十分に検討して運搬方法を決めています。そのため、現場に応じた様々な運搬方法があるのです。
みなさんもどこかへ出かけた際に、ボーリングマシンと櫓を見つけたら、どのようにそこへ機材を運び入れたのか、ぜひ思いを巡らせてみてもらえると嬉しいです。
↓
↓
↓
※このブログは、XサーバーとXサーバードメインを使って作っています。Xサーバーなら安定性はもちろん、WordPressの導入も楽々です!ぜひオリジナルのブログを作って発信してみませんか?


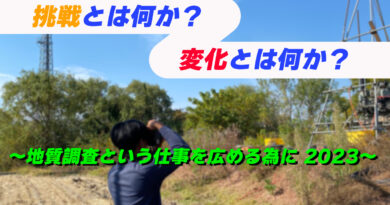
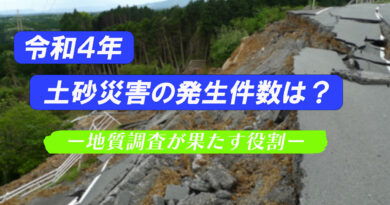
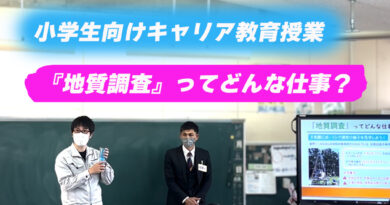
ピンバック: 設計書通りにはいかない? -河道内での調査方法の検討と実践例- - ネガルタス -背中のキズは恥じゃない-
ピンバック: 令和4年度『青本』の変更点は?-モノレール運搬 積算方法の変更- - 地質調査×イメチェン ブログ